排気量が250ccを超えるバイクを所有していると避けて通れないのが「車検」です。特に初めての車検は、費用や手続き、整備内容など分からないことだらけで不安を感じるライダーも多いはず。
本記事では、排気量ごとの車検の有無から、ユーザー車検と代行の違い、必要な費用や整備内容まで、バイクの車検に関する疑問をわかりやすく解説します。
愛車を安心して乗り続けるために、ぜひ参考にしてください。
バイクの車検とは?
バイクの車検とは、公道を安全に走るためにその車両が国の基準を満たしているかどうかを定期的に確認・証明する制度です。正式には「自動車検査登録制度」と呼ばれ、排気ガスやブレーキ性能、灯火類、タイヤの状態など、安全性と環境基準をチェックします。対象となるのは、排気量が250ccを超えるバイク。これらは車と同様に、新車登録から3年後、その後は2年ごとに車検を受ける必要があります。
車検を受ける場所は、国が運営する運輸支局(陸運局)で、バイク販売店、または用品点などの車検代行業者に依頼するのが一般的です。また、自分で手続きを行う「ユーザー車検」という選択肢もあり、費用を抑えたいライダーに人気です。
「バイクの車検って面倒くさそう」と思うかもしれませんが、制度の内容や方法を理解すれば、費用も手間も最適化できます。
排気量と車検の関係
.jpg)
バイクの車検が必要かどうかは、排気量によって明確に区分されています。これを知っておくだけでも、自分のバイクにどのような手続きが必要かが一目でわかります。
まず、排気量が251cc以上のバイク(いわゆる「大型二輪」「普通二輪の上限クラス」)は車検が義務付けられています。新車の場合、初回の車検は登録から3年後、その後は2年ごとの更新が必要です。定期的に法定点検と検査を通し、車両の安全性や環境への配慮が保たれているかをチェックします。
一方で、排気量が250cc以下のバイクには車検義務がありません。これは「軽二輪」と呼ばれるクラスで、ナンバープレートの色は白地に緑文字が基本です。さらに、125cc以下のバイク(原付二種)、50cc以下の原付一種も同様に車検は不要です。
ただし、車検が不要ということは「整備も不要」ではありません。特に250cc以下のバイクは日常点検や消耗品の管理を怠ると、故障や事故につながるリスクが高まります。車検がない分、自己責任でのメンテナンス意識が求められます。
愛車の排気量を把握し、自分に必要な手続きとメンテナンス体制を理解しておくことは、安全で快適なバイクライフの第一歩と言えるでしょう。
チェックポイント!
・車検の対象は排気量が251cc以上のバイク
・普通二輪(251cc~400cc)と大型二輪(401cc~)の検査項目は同じ
車検が必要になる年数とは?

バイクの車検は、排気量だけでなく登録からの経過年数にも関係しています。車検のスケジュールは法律で定められており、排気量251cc以上のバイクを対象に、新車登録から3年後に初回の車検、以降は2年ごとに定期的な更新が必要です。
たとえば、2022年に新車登録した大型バイクなら、最初の車検は2025年。その後は2027年、2029年と2年おきに繰り返されていきます。この年数サイクルに沿って、車両の安全性・環境性能を維持することが制度の目的です。
一方で、中古バイクを購入した場合は、前のオーナーが受けた車検の「残り期間」が引き継がれます。そのため、購入直後にすぐ車検が必要になるケースもあるので注意が必要です。バイクショップなどで中古車を購入する際は、「車検残」の有無と有効期限を必ず確認しましょう。
また、しばらく乗っていないバイクを再登録する際にも、年数に応じて新たに車検を通す必要があります。特に車検切れのまま放置していた場合は、整備項目が増え、費用や手間もかかるので要注意です。
バイクの車検は、「年数管理」が基本。車検証に記載されている有効期限をこまめにチェックし、忘れずに計画的な準備を進めましょう。
チェックポイント!
・車検は新車登録から3年後に初回の車検、以降は2年ごとに更新
・中古車を買うときは車検の有無を確認しよう
バイクの車検を受けられる場所(陸運局)とは?

バイクの車検は管轄の「陸運局」で行います。正式には運輸支局(国土交通省の地方機関)のことを指し、バイクや車の車検・登録・名義変更などを行う国の検査施設です。この運輸支局にバイクを持ち込み、検査ラインを通して車検を受けます。
全国各地に運輸支局は点在しており、車検の際はバイクの登録地を管轄する支局に予約を入れて来庁するのが基本です。施設内には「予備検査場」「書類受付窓口」「検査ライン」などが整っており、一般のユーザーでも利用できますが、事前の整備や書類準備が不可欠です。
検査当日は、受付→書類提出→検査ライン通過→合否判定という流れで進行し、全体で1~2時間程度かかるのが一般的です。
チェックポイント!
・ユーザー車検、代行業者のいずれも車検は管轄の運輸支局(陸運局)で行う
バイクの車検を受ける方法は?

バイクの車検を受ける方法には、大きく分けて「ユーザー車検」と「車検代行」の2種類があります。どちらも車検を通すという目的は同じですが、手間・費用・信頼性に大きな違いがあります。それぞれの特徴を理解することで、自分に合った方法を選ぶことができます。
ユーザー車検
ユーザー車検とは、バイクのオーナー自身が運輸支局(陸運局)にバイクを持ち込み、必要書類の準備から検査ラインの対応までをすべて自分で行う方法です。必要な整備はあらかじめ行っておく必要がありますが、車検の手続きや検査は基本的に本人が行います。
メリット
最大のメリットは費用が安く抑えられることです。代行手数料や整備工賃がかからないため、車検にかかるのは法定費用(自賠責保険・重量税・検査手数料など)のみ。車検代を1万円台に抑えることも可能です。また、自分で整備状況を把握できるので、バイクへの理解も深まります。
デメリット
一方で、知識や準備が不十分だと大きな負担になる可能性があります。陸運局での書類の記入や検査ラインでの対応、光軸調整など慣れていないと戸惑うポイントも多く、初めての人にはハードルが高め。また、整備不良で不合格になると再検査や整備が必要になり、時間も労力も増します。
また、陸運局は土日祝日及び年末年始は閉鎖しています。バイクの登録や車検は平日のみの対応のため、平日働いている方は注意が必要です。
車検代行
車検代行とは、整備工場やバイクショップなどの専門業者に車検手続きを一任する方法です。点検・整備から検査、書類作成、車両の搬送までをまとめて行ってくれるため、手間が大きく省けます。特に初めて車検を受ける方や、忙しくて時間がとれないライダーに人気があります。
メリット
車検代行の最大のメリットは、安心感と手軽さです。経験豊富な整備士が法定点検に加えて、必要な調整や部品交換まで行ってくれるため、合格率が高く、後々のトラブルも少なくなります。また、不備や整備漏れをプロが事前にチェックしてくれるため、再検査のリスクも低くなります。さらに、納車・引き取りサービスや代車の貸し出しを行っている業者も多く、日常生活への支障も最小限で済むのが魅力です。最近では、LINEなどで見積もりや予約ができる業者も増えており、利便性はますます高まっています。
デメリット
デメリットとしては、費用が高くなりやすい点が挙げられます。法定費用に加え、整備料や代行手数料(1~3万円程度)がかかるため、合計で4~6万円ほどになるのが一般的です。また、業者によって対応内容や料金に差があるため、事前の見積もり確認や比較が大切です。
とはいえ、確実かつスムーズに車検を済ませたい方にとっては、費用以上の価値がある方法と言えるでしょう。
車検に必要な書類は?

バイクの車検を受けるには、いくつかの重要書類を事前に用意しておく必要があります。とくにユーザー車検を考えている場合は、ひとつでも不足すると受付ができず、その日の検査が無駄になってしまうので要注意です。以下が、一般的に必要となる書類一覧です。
1. 自動車検査証(車検証)
現在登録されているバイクの情報が記載された基本書類。原本が必要です。紛失している場合は、再発行手続きが必要になります。
2. 自賠責保険証明書
ユーザー車検の場合は「前の保険証+新たに契約した保険証」の両方が必要です。代行業者に依頼する場合は、新たな自賠責保険の加入も代行してくれます。
3. 点検整備記録簿(または整備記録票)
法定12か月点検を実施し、その結果を記入した整備記録です。自分で整備する場合も、チェックリスト形式で記載して提出します。代行業者整備の場合は、整備工場で発行してくれるので不要です。
※点検整備記録簿を紛失した場合などは無くても車検を受けられますが、車検証に「点検記録簿なし」と記載される場合があります。 また、車検後は点検整備を行い記録をつける必要があります。
4. 継続検査申請書
これらは運輸支局にある窓口で当日入手できますが、事前に入手し記入してから持参するとスムーズです。代行業者に依頼する場合は不要です。
チェックポイント!
・ユーザー車検の場合は1~4全ての書類が必要
・代行業者に依頼する場合は1~2の書類を用意すればOK
・以前は必要だった軽自動車税納税証明書は電子化に伴い不要になりました
バイクの車検費用はいくらかかるのか?

バイクの車検で気になるポイントといえば、やはり「総額でいくらかかるのか?」という点でしょう。車検費用は大きく分けて、国に支払う「法定費用」と、整備や代行にかかる「整備費用」の2つに分かれます。バイクの状態や選ぶ車検方法によって金額は大きく変わるため、それぞれの内訳をしっかり把握しておくことが重要です。
法定費用
バイクの車検にかかる「法定費用」は、国によって定められている最低限必要な支払い項目です。これはどんな方法で車検を受けても必ず発生する費用であり、ユーザー車検であっても、業者に依頼する場合でも同額です。主に次の3つの要素で構成されています。
自賠責保険
自動車損害賠償責任保険(自賠責)は、事故の被害者を救済するために加入が義務付けられている保険です。バイクの場合、車検時には2年間分の加入が必要となります。2025年現在、251cc以上のバイクの自賠責保険料は2年で約8,760円程度となっています(保険会社によって若干の差あり)。
重量税
バイクの重さに応じて課される税金で、新車時や車検時に支払います。重量というよりは排気量区分で決まっており、バイクの場合はシンプルで、新車であれば一律で3,800円(車検1回ごと)です。ただし、新車登録から13年・18年と経過すると、環境性能の観点から下記の通り増税されます。
・新車登録から12年未満=3,800円
・13年超え18年未満=4,600円
・18年超=5,000円
印紙代
車検の検査や車検証の発行などに伴い、国や地方公共団体に支払う手数料です。
1,800円
法定費用の合計金額
自賠責(2年)8,760円 + 重量税(12年未満)3,800円 + 印紙代1,800円 = 14,360円
代行業者に依頼した場合の手数料(点検整備費用を除く)
車検の代行サービスに依頼した場合の手数料は概ね1.5万円前後です。これにプラスして整備費用がかかります。
チェックポイント!
・法定費用の3つを合計すると概ね1.4万円前後
・車検の代行手数料は1.5万円前後+整備費用
次はこれに上乗せされる、整備や交換にかかる実質的なコスト=整備費用について詳しく見ていきましょう。
整備費用
法定費用に加えてバイクの車検時に必要となるのが、整備費用です。これはバイクの状態や整備内容によって大きく変動し、1万円台で済むこともあれば、5万円以上かかることもあります。とくに古いバイクや長期間メンテナンスしていない車両では、交換部品が多くなりがちです。
整備費用は、法定で義務づけられた「点検整備記録簿」に基づき、エンジンまわり・ブレーキ・灯火類・保安部品など多岐にわたる項目をチェックし、必要に応じて調整や部品交換を行います。
主なチェックポイントとしては、ヘッドライトの光軸、ウインカーやテールランプなどの灯火類、ブレーキの効き具合やパッドの摩耗、マフラーの排気音とガス規制への適合性、そしてタイヤの溝や空気圧などがあります。これらのどれかに不具合があると、検査で不合格となる可能性があるため、事前の整備は欠かせません。
また、整備をプロに依頼する場合は、基本整備料に加え、部品代や工賃が加算される形になります。たとえば、ブレーキパッドの交換だけでも数千円~1万円程度の追加費用が発生することもあります。
次の各項目では、車検のチェック項目と整備費用がかかりやすいポイントごとに詳しく解説していきます。
灯火類

灯火類は、車検時のチェック項目の中でも非常に重要な保安部品のひとつです。ここで不備があると、車検に通らないどころか、日常走行中の事故リスクも高まります。点灯の有無だけでなく、明るさ・色・点滅の状態までもが細かく検査されるため、しっかりと確認・整備しておく必要があります。
対象となるのは、ヘッドライト(前照灯)・ウインカー(方向指示器)・ブレーキランプ・テールランプ・ナンバー灯などです。特にウインカーやブレーキランプは点滅速度やタイミング、取り付け位置などもチェックされ、LEDバルブへの交換などをしている場合には規格外になっていないか注意が必要です。
たとえばウインカーは、点灯色が橙色で毎分60~120回の点滅である必要があり、それを超えると不合格となります。純正品をLEDに換装した際に、抵抗を入れずにハイフラ状態になるケースも多いため注意が必要です。
また、ナンバー灯が切れていると意外に見落としがちですが、これも車検不合格の原因になる代表的なポイントです。暗所での視認性確保が目的のため、点灯しているかを必ず確認しましょう。
交換が必要な場合、バルブ1個あたり数百円~数千円程度ですが、LEDやカスタムパーツを使用していると、より高額になることもあります。カスタムする場合は車検対応のものに交換するのが確実です。
チェックポイント!
・ランプ類は点灯の他、色や取り付け位置なども細かく決まっているので注意
・カスタムする場合は車検対応か確認しよう
ブレーキ周り

ブレーキはバイクの安全を守る最重要パーツのひとつであり、車検においても厳しくチェックされる項目です。
車検場での検査方法は、ローラー台の上に車両のタイヤを乗せます。検査員が合図を出したタイミングでブレーキをかけ、ローラーが一定の時間以内に止まれば合格です。
▼車検前にチェック・整備しておきたいポイント
ディスクブレーキ搭載車の場合、ブレーキパッドの厚みが残っているかは基本中の基本です。パッドが1mm以下に摩耗している場合、制動力が不足していると判断されかねません。交換費用は車種にもよりますが、片側3,000〜6,000円程度+工賃が目安です。
また、ドラムブレーキの場合は、シューの摩耗や遊びの調整をチェックし、必要に応じて清掃・交換・グリスアップなどを行いましょう。
パッド以外にも、ブレーキフルード(オイル)は、長期間交換しないと吸湿性により性能が低下し、効きが悪くなるだけでなく、安全性も損なわれます。フルードの汚れ・量・漏れがないかをチェックし、不安がある場合は交換しましょう。フルード交換の相場は2,000〜4,000円程度です。ホース類のひび割れや劣化、マスターシリンダーからの漏れも見逃せないポイントです。とくに10年以上前の車両では、ゴム製パーツの劣化による交換が必要になるケースも少なくありません。
ブレーキは“効いて当たり前”と思いがちですが、実は日頃から気を配っておくべき消耗系の代表格。車検をきっかけに、しっかり状態を確認しておくことが重要です。
チェックポイント!
・ブレーキはパッドの他、フルードやホース類もチェックしよう
スピードメーター

スピードメーターは、車検における保安基準のひとつとして必須の装備です。速度表示が正常に行われるか、走行中に確実に針やデジタル表示が作動するかがチェックされます。たとえバイクが問題なく走る状態であっても、スピードメーターに異常がある場合は車検不合格となるため、事前確認が欠かせません。
検査では、スピードテスターと呼ばれるローラー台のような専用装置を使って速度表示の誤差を確認します。タイヤを乗せたローラーが回転し、スピードメーターが時速40kmを指したときに、ボタンで合図をします。合図のタイミングが、ローラーの時速と合致すれば合格となります。
また、速度の誤差の他にも、メーターケーブルが切れかかっている、バックライトが点灯しないなどの不具合も指摘の対象となります。デジタルメーターの場合は液晶の表示不良や、センサー系のトラブルにも注意が必要です。
カスタムメーターを取り付けている車両は、車検対応であるかどうかを事前に確認しておきましょう。車種によっては、社外品で配線の取り回しや表示精度に影響が出るケースもあります。
万が一、スピードメーターが不合格となった場合、ケーブル交換やメーター本体の修理・交換が必要です。費用は数千円〜1万円超+工賃となることが一般的です。
チェックポイント!
・カスタムメーターに交換している場合はスピードの誤差に注意
マフラー関連

マフラーは、バイクの排気音や排気ガスに関わる重要なパーツであり、車検では騒音規制や排ガス規制に適合しているかが厳しくチェックされます。とくに社外マフラーに交換しているバイクは注意が必要で、音量や認証ラベルの有無によってはそのままでは車検に通らないこともあります。
騒音規制
年式によって排気音量の基準は異なります。
・1985年以前に製造されたバイク:音量規制なし
・1986~2000年に製造されたバイク:250cc以上/99db以下
・2001年以降に製造されたバイク:250cc以上/94db以下
・2014年4月以降に製造されたバイク:車種の基準値+5db以内(基準値が79db以下ならば84db)
また、2016年10月以降に製造されたバイクの場合、音量が基準をクリアしていても下記の認証マークがあるマフラーでないと車検に通らないので注意が必要です。
・JMCAマーク(全国二輪用品連合会の認証マーク)
・Eマーク(通称ヨーロッパ規格と呼ばれる、車検認証品を示すマーク)
・自マーク(装置型式指定品表示、国内メーカーの純正マフラーに刻印)
排ガス規制
2007年(平成19年)の排ガス規制(施行は平成17年)により、該当車両で社外品のマフラーに交換している場合は車検時に「排出ガス試験結果証明書(通称:ガスレポ)」が必要です。
▼ガスレポが必要になるケース
・排ガス規制の対象になっている1999年以降のバイク
・かつ、ノーマルで触媒装置(キャタライザー)が装着されているバイク
・かつ、社外マフラーに交換されているバイク
▼平成19年排ガス規制対象の判別方法
・国産車:型式が「EBL-〇〇」になっている
・輸入車:備考欄「19年排出ガス規制適合」の記載がある
JMCA認証マフラーの場合、必要な場合はガスレポが同梱されているので紛失しないようにしましょう。(紛失した場合はメーカーに再発行してもらえますが基本有料です。)また、純正マフラーやJMCA認証品でも、触媒の劣化により排ガスの規制値をクリアできない場合は車検に通りません。
マフラー関連の整備費用は、純正戻しで1万円前後+工賃、交換用マフラーの購入となると数万円かかることもあります。カスタム派のライダーは、「車検対応品かどうか」を事前に必ずチェックしましょう。
チェックポイント!
・マフラーの騒音規制・排ガス規制は車両年式によって基準が異なる
・カスタムする場合はJMCA認証のマフラーなら安心
ホーン

ホーン(警音器)は、バイクの安全装備として法律で装着が義務づけられているパーツのひとつであり、車検時にも確実に音が鳴るかどうかがチェックされます。一見地味な存在ですが、不具合があると車検不合格の対象になるため、忘れずに点検しておきたいポイントです。
▼ホーンの保安基準
・車両の前方7mの位置において音量が
112dB 以下 93dB 以上(※平成15年以前に製造されたバイク)
112dB 以下 87dB 以上(※平成16年以降に製造されたバイク)
・ホーンの音は変化や断続をしてはいけない
・サイレンや鐘の音などは不可
・運転者が音の大きさや音色を変化させることができるものは不可
車検でのチェックはシンプルで、スイッチを押して「正常な音量で音が出るかどうか」が確認されます。鳴らない場合や音が極端に小さい・不明瞭であるといった場合は不合格です。また、ホーンの音量に極端な変化があったり、法律で禁止されているミュージックホーンやサイレンタイプの装着もNGなので注意が必要です。
点検時には、ホーンの音が鳴るかを確認するだけでなく、ハンドルスイッチや配線の接触も含めたチェックをしておくと安心です。もし不具合が見つかった場合、ホーン本体の交換は2,000〜4,000円程度+工賃で済むことが多く、比較的手軽な整備で改善可能です。
光軸(ヘッドライト)

車検時にもっとも落とされやすい項目のひとつが、ヘッドライトの「光軸」です。光軸とは、ヘッドライトの光が照らす方向・角度のことで、これが基準から外れていると、前方を正しく照らせず、対向車にまぶしさを与える危険性があるため、車検では厳しくチェックされます。
検査ではバイクを専用の光軸テスターの前におき、バイクにまたがり水平な状態にしたうえでエンジンをかけ、ヘッドライトをハイビーム*で点灯させます。光軸および光量が基準を満たしていれば合格です。
※検査場によってはロービームで検査する所もあります。
▼車検の光軸基準
検査機の1m前、10m前からそれぞれ照射した際に、光軸のズレが以下の範囲に収まっていれば合格基準となります。
・左右のズレ:27cm以内に収まっているか
・上部のズレ:10cm以内に収まっているか
・下部のズレ:地面からライトまでの距離のうち20%以内に収まっているか
照射範囲が規定から外れていると、たとえ明るく点灯していても不合格となります。特にカスタムヘッドライトやHID・LED化している車両は明るさや配光が基準に達せず不合格になりやすいので注意しましょう。
光軸がズレる原因としては、転倒による歪みやサスペンションの沈み込み、マウントの緩みなどが考えられます。自分での調整は難しいこともあり、専門のテスター設備がある整備工場での調整が安心です。
光軸調整の費用は、1,000〜3,000円程度で済むことが多く、事前に整備工場で測定・調整をしておけば、検査ラインでの不合格リスクを大きく下げることができます。
チェックポイント!
・ユーザー車検の場合は陸運局の近くにあるテスター屋(予備検査場)を利用しよう。調整は当日しないとズレる可能があるので注意。
タイヤ

タイヤは、路面との唯一の接点であり、バイクの走行性能と安全性に直結する重要パーツです。車検でチェックされるポイントはタイヤの溝の深さです。
▼タイヤの法定基準
タイヤの溝は0.8mm以上の深さを有していること
まず最も重視されるのが、スリップサインの位置と残り溝の深さです。一か所でもスリップサインが露出していたり、残り溝が0.8mm未満の場合は、即不合格となります。たとえ走れる状態であっても、基準に満たなければ交換が必須です。
点検時は、サイドウォールのひび割れや硬化、変摩耗がないかもチェックしておきましょう。タイヤは経年劣化するため、たとえ溝が残っていても、5年以上使用したタイヤはゴムが硬くなり、グリップ力が低下している可能性があります。車検時には、製造年週(タイヤの側面に記載)も確認しておくとよいでしょう。
空気圧も重要です。規定よりも大幅に低下していると、車検ラインでのテスト中にハンドリングが不安定になったり、再検査になることがあります。事前に適正な空気圧に調整しておくのが基本です。
タイヤ交換費用は前後セットで2〜4万円程度+工賃(1万円前後)が相場です。車検を機に新調しておくことで、安心して次の2年間を走ることができます。
チェックポイント!
・タイヤのスリップサインは全か所チェックしよう
ほか外装部品や気を付けたいポイント
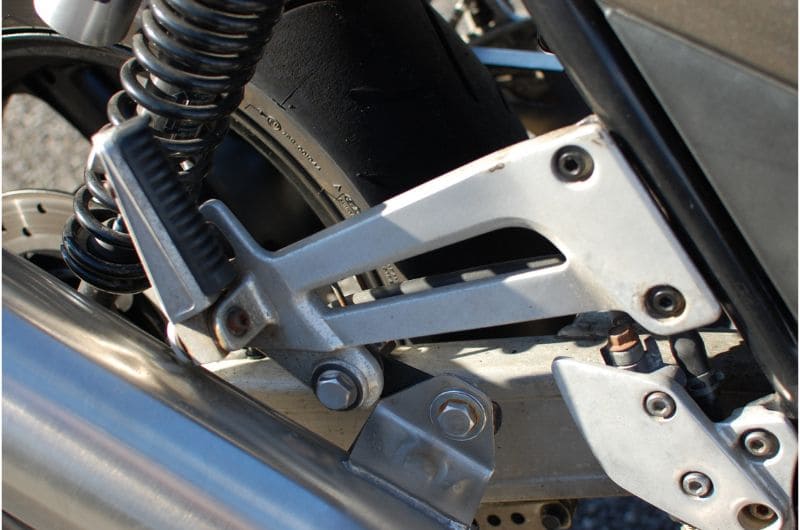
バイクの車検では、外装パーツの状態も意外と細かくチェックされます。外装の問題は「走れるから大丈夫」と思われがちですが、保安基準に適合していない場合は見た目の破損や改造でも不合格になることがあるため注意が必要です。
▼乗車定員2名登録に注意
車検証に乗車定員が2名と記載されている場合、シングルシート化やタンデムステップ、純正のグラブバーやシートバンド等を取り外した状態では車検に通りません。
▼ミラー、ハンドル周り
ミラーの鏡面の大きさや取り付け角度は明確に規定されており、左右両方が基準に適合していない場合はアウトです。カスタムミラーを取り付けている場合は要注意。
また、ハンドルを交換している場合、車検証に記載された寸法から「長さ±3cm、幅±2cm、高さ±4cm」以上となる場合は構造変更検査が必要になります。
▼ナンバー周り
また、ナンバープレートの取付角度も重要なチェックポイントです。近年の法改正により、ナンバーが斜め上向きや横向きに取り付けられていると不正改造と見なされ、不合格になる可能性があります。また、「フェンダーレス化」などで反射板(リフレクター)が無い場合も不合格となるので注意しましょう。
▼リアフェンダー
さらに、リアフェンダー(泥除け)の有無や長さも確認されます。タイヤからの泥跳ねや水しぶきを抑える役割があり、これが不十分と判断されると保安基準不適合とされることがあります。
▼外装の破損なども注意
外装のひび割れや、尖った部品・突出物なども、歩行者との接触リスクが高いと判断されれば不合格となります。特にカウルの破損やビスの飛び出しなどは、意外と見落とされがちです。
見た目だけでは判断できないのが外装類の車検基準。「カスタム=NG」ではないものの、「車検対応かどうか」を事前に確認しておくことが大切です。
まとめ
バイクの車検は、「面倒」「高い」といったイメージを持たれがちですが、制度の仕組みや費用の内訳を理解すれば、必要以上に不安を感じることなく、計画的に対応できる手続きです。
愛車をこれからも安心して走らせるために、次回の車検に向けた準備を、今から少しずつ進めておきましょう。
ナップスのバイク車検は「選べる・お得・安心!」

ナップスではお客様のご都合に合わせて、3つのプランから最適なサービスを選べるバイク車検をご用意!
最安のエコノミー車検なら、「点検整備費用+法定費用」を合わせて(税込)41,860円~の納得プライス。
お見積りは無料なうえ、早めのご予約で割引になるサービスや一部の作業工賃が無料など、とってもお得♪
煩わしい書類の準備や整備が不要なナップスの車検をぜひご利用ください!
>>あなたの最寄りのナップス店はこちら!